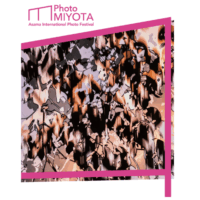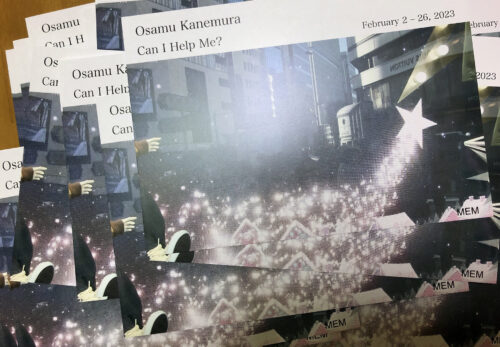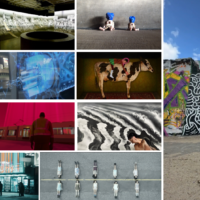“Marshmallow Brain Wash”, ”Killing Agent” by Osamu Kanemura
Dates: November 10 – December 9, 2018
Venue: HIJU GALLERY (Osaka, Japan)
Overview
Osamu Kanemura’s black-and-white and movie work had shown.
“Marshmallow Brain Wash” is over 100 of his black-and-white prints. He prints the 20 x 24-inch prints for the exhibition. “Killing Agent” is his video installation, comprising four films and 36 digital color prints. The gallery has two parts, so these two shows are independent of each other.
金村修のモノクロプリント100点以上で構成される「Marshmallow Brain Wash」のための20×24インチのプリントは金村自ら暗室でプリントしたものだ。「Killing Agent」は4本の映像と36点のデジタルカラープリントからなる映像インスタレーションである。ギャラリーは二つのスペースに分かれているため、これら二つの展示は互いに独立している。



Statement
モノクロ写真は対象を色彩ではなくフォルムで捉えるのに適しているフィルムだと言われていたのを覚えている。初心者の段階でカラー写真を始めると色彩に誤魔化されて対象をフォルムとして捉えられなくなるというそんな考え方が理由だったようだ。フォルムを強調するモノクロ写真は、美術でいえば対象をきちんと把握するデッサン的な扱いとして使用されていたのだろうか。対象の形を確実に獲得するために使用されるモノクロ写真は、現実世界の溢れるような色彩を統御するための装置として使用されるのであり、色彩に誤魔化されるなという言い方には、色彩だけで見ているときちんと世界を把握できずに、混沌とした現実の世界にただ巻き込まれてしまうという教訓的な意味合いがあるのだろう。巻き込まれないで写真家としての主体性を確立させるために、モノクロ写真は使用される。
モノクロ写真は白と黒の色しか持たない写真ではなく、白から黒の間に表れるグレーのなだらかなグラデーションを中心に構成された写真であり、プロヴォーグに代表されるような白と黒の強烈な対比で成り立っている写真はむしろ異端な写真だ。グレーのグラデーションを基軸とした黒から白までの色が一枚の画面の中で調和した穏やかな色彩を持った写真だと思う。曖昧な色の重なり合いで成立しているモノクロ写真では、フォルムもまたハイコントラストの写真のようにものの輪郭を強調し、白と黒の単純な対立に還元されたフォルムではなく、フォルムに還元されたものの輪郭が幾十にも重なり合うことでものの姿が複数な線として提出される。空を覆い隠すようなビル群の上を電線が重なって写された東京の姿は、現実的な東京の街であるよりも、無数の線に分解されたフォルムとして現われる。モノクロ写真のフォルム性は、デッサンのように対象の輪郭をはっきりと描くためのものではなくて、対象をフォルムに転化することでそれらを無数の線に分解することではないだろうか。それはものを把握するためではなく、ものの同一性を保証する輪郭を複数化することでその同一性を破壊するのだ。無数に分解された線が重なり合うモノクロ写真では、対象の輪郭がクリアに表れるというよりも輪郭が無限に分割されていくような感じを受ける。
対立的な構図が喚起させる攻撃的なイメージよりもグレーのグラデーションを基調にしたモノクロ写真のトーンは、グレーが様々な色の混合で成立している色であるようにもっと曖昧な感じを思わせるだろう。その構造は対立的であるよりもレイヤー的な構造であり、階調という言葉が示すようにそのなだらかな色彩によって成立している遠近法は、破綻もなく調和したまま重なり合っている。それに対して画面に写っているものは、調和しないまま重なり合い、遠近法的な階層を無視したかのようにそこに写される。グレートーンのグラデーションが表現する調和した色彩と遠近法を無視したものの集積。そんな調和と破綻が画面の中に同時に表れるのが写真であり、トーンが示すなだらかなレイヤー構造に対立するように様々なものが調和を無視して写ってしまう写真は、現実をコラージュのようにつぎはぎだらけの別の現実に変質させるだろう。
写真は絵画と同じように他のメディアと比べて、比較的短時間で画面のものを理解することができる。特に音楽や映像と比べると時間の拘束から自由であり、それらのメディアと比べると瞬間的と言っていいぐらい早い時間で理解することができる。けれど写真は概念や言葉という補助線を必要としないで、瞬間的に理解できるような強い視覚性を持ったメディアなのだろうか。写真を見ることは、視覚にだけ還元できるのだろうか。
現実の対象と密接な関係を持つ写真の場合、写っているものをフォルムだけで見ようとするのは不可能に近いのではと思う。フォルムとして見ようとしても写された対象のイメージが抱えている、ものの意味やその人がその対象に対して抱いている記憶が次々と喚起されていくことで、視線はフォルムだけに集中することができなくなる。視線が表面を流れ続けようとしても、写されているものが意味や記憶を喚起させ続け、それは視線にとってノイズとして機能するだろう。写真は視覚だけで成立することができず、視覚以外の要素が必要とされるのであり、純粋に見ることだけで成立することができない。
写真を見ることは、「見る」ことと同時に「読む」ことが重なってくる。写された犬を見れば、その犬に対して写真史的、個人的な記憶が喚起され、そのような記憶を重ね合わせながら写真は見られるだろうし、様々なものが画面に同時に写されるコラージュとしての画面を「見る」ことは、視線に対して無理な跳躍を要求するだろう。「見る」ことから「読む」ことを切り離すことができず、つねに視線の跳躍を要求する写真を「見る」ということは、画面からあらゆるノイズを削ぎ落として瞬間的に「見る」視覚だけに還元させようとする純粋視覚に対して、「読む」という瞬間的な判断を遅延させる持続の時間が妨害し続ける。それは「見る」という瞬間的な理解とは真逆の横に動き続ける視線の時間性が重なり合うことだ。瞬間が時間から切り離され垂直に上に上にと上昇する超越性を志向する時間なら、写真を見る時間は写っている対象に引っ張られるようにして「見る/読む」のであり、上昇することもなく表面を動き続ける。それはものの表面を上昇することもなく、ただ表面の上をぐるぐると回り続ける時間なのではないだろうか。
「読む」ものとしての写真は、では一体そこに何を読もうとしているのだろう。そこに何らかの物語を読もうとしているのなら、写真は物語とは基本的に相入れないメディアであり、物語をそこに見いだすのは難しい。物語は基本的に一つの視点で語られるものであり、写真は一つの視点で語ることができない。写真は様々な要素が一枚の画面の中で統合しないまま定着されるものだから、そのようなコラージュ的な画面を物語のように一つの視点で語るのは難しいだろう。ましてその様々な画面を支える基本的な底面は、フィルムの粒子という細胞のように丸い抽象的な形が写真のイメージを支えている。抽象的な丸の構成によって成り立つ写真は、写真に目を近づければ丸い粒子が羅列されているだけの抽象的なものに見え、離れて見れば具体的な現実の被写体に見えるというように、写真は抽象と具体の両極を動き続けるメディアであり、そのような二極化された形態を持つ写真に物語を語ることができるのだろうか。物語を写真に読み取ろうとしてもそこには粒子という抽象性が物語のイメージを妨げるだろうし、粒状性の美しさやグラデーションの美しさ、画面のコラージュ性、モノクロ写真が強調するフォルマテックな要素も物語の進行を妨げ続ける。ボードレールが彫刻の退屈さについて書かれた文章の中で、絵画は一つの視点で成り立っているから面白いのであって、彫刻は遠のいたり、近寄りながら間合いを詰めたりして見るので見え方が不確定で面白くないというようなことを書いている。写真もまた人によっては見ているところが違うだろうし、今日は画面の右側が気になるけれど、昨日は画面の左側が気になっていたというように、見るたびに見るところが変わっていく。写真はそのような意味で、彫刻の退屈さを共有しているだろうし、視点がつねに変わり続ける写真の見え方に、いわゆる物語として写真を見ることは不可能なのではないだろうか。
写真は対象を正しく写し出す。写された犬は犬であり、机は机として写される。写された対象を何か違うものに間違える可能性は低く、対象を正しく捉えることのできる写真を見ると、誰もがそこに写真の犬ではなく現実の犬を見ているかのような錯覚に襲われる。写真はそこでは透明なメディアとして扱われ、写真を見ようと思っても、現実の被写体の存在が写真を見ることを妨害し続け、そこに写真が現われることはないだろう。わたし達は写真を見ることができるのだろうか。
現実をカメラのフォーマットで切り取ることで現われる写真は、ドーナツの穴の空洞に似てそこに実体として現われることができない。写真は被写体と共に現われるのであり、そこに写っているのは写真ではなく、再現された被写体のイメージであり、何の助けも借りずに写真自身で自らを現すことができないのだ。写真を思考することは、何もない空洞のドーナツの穴を思考することに似ているように思う。ドーナツの穴について思い浮かべるとき、それは穴だけを思い浮かべることができないように、ドーナツの穴についての思考は、つねにドーナツの全体を思い浮かべなければ穴について思考することも現われることもできない。写真もまた被写体を思い浮かべなければ写真が現れてくることができないように、写真自体は何もない空洞の穴に近い存在ではないだろうか。ドーナツの穴がドーナツの全体に依存しているように、印画紙やフィルムや被写体に依存することでしか存在できない写真は、それ自体では実体化することのできないドーナツの穴のような存在だろう。それはそこにありながらもそれ自体で自律的に存在することができない穴なのだ。
金村修


Individual images / Marshmallow Brain Wash